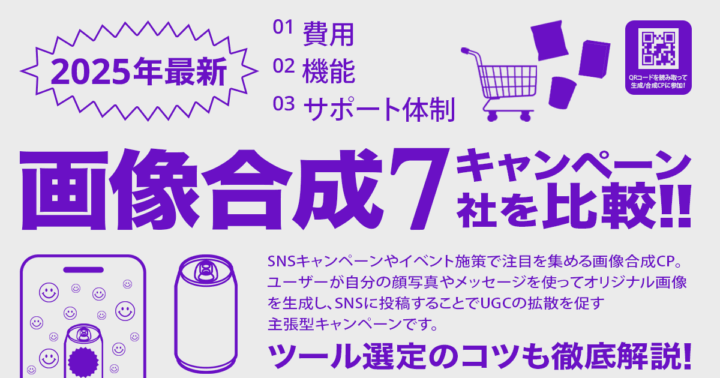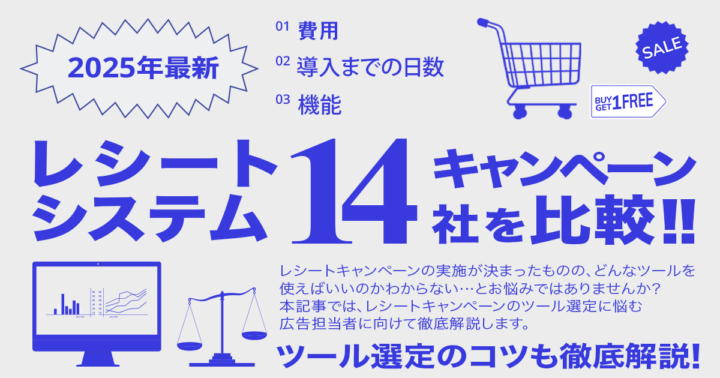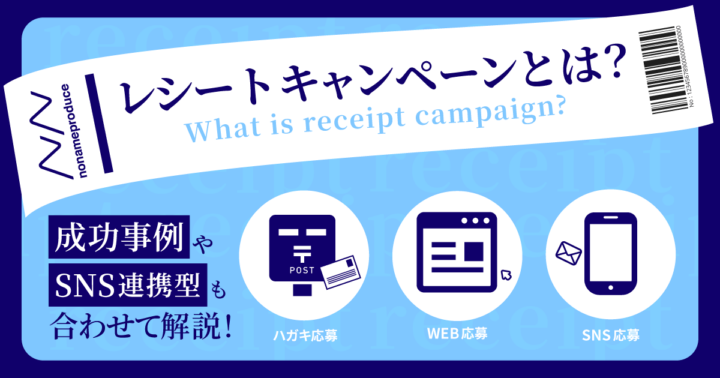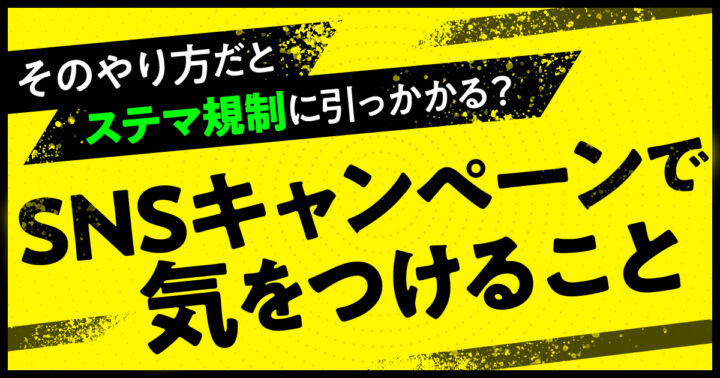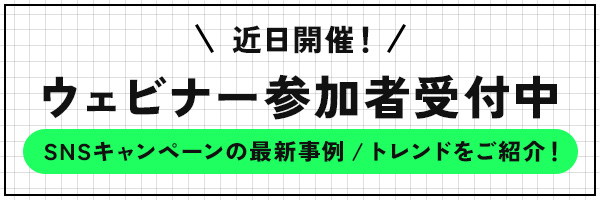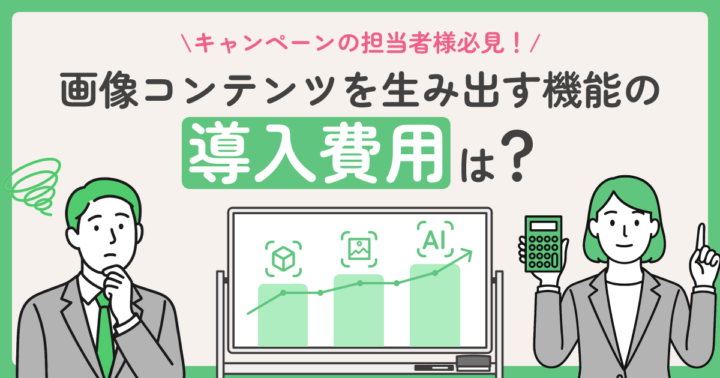
n2p blog
キャンペーンやSNSの
"ためになる"情報を
執筆しています。
【2025年最新版】ハッシュタグキャンペーンのやり方|誰でもできる!完全ロードマップ

更新日:2025.10.16 (公開日:2025/08/06)
SNSを活用したプロモーション施策の中でも、手軽かつ高い拡散力を持つ「ハッシュタグキャンペーン」。ユーザー参加型の施策として、認知拡大・UGC(ユーザー生成コンテンツ)の収集・エンゲージメント向上など、多くの効果が期待できることから、企業・自治体を問わず活用されています。
本記事では、1000件以上のSNSキャンペーンを支援してきたNoname Produceの実績と研究をもとに、ハッシュタグキャンペーンを成功に導くためのノウハウを、ロードマップ形式でわかりやすく解説します。目的設定や投稿設計に加え、つまずきやすい注意点や課題への対処法まで網羅しているので、ぜひキャンペーン企画の参考にしてください。
「なんとなく」ではなく、「成果に直結する」ハッシュタグキャンペーンを実現したい方に向けて、2025年最新版のノウハウをお届けします。
【この記事はこんな方におすすめ】
- ハッシュタグキャンペーンをやってみたいけど悩んでいる方
- SNS運用やプロモーションに課題を感じている方
- ユーザーの声(UGC)を活かしたマーケティング施策を検討している方
目次
ハッシュタグキャンペーンとは?
ハッシュタグキャンペーンとは、SNS上で指定のハッシュタグを付けて投稿するだけで簡単に参加できるキャンペーンです。
商品購入や公式アカウントのフォローを応募条件に加えることで、ブランド認知やエンゲージメント向上、顧客層の分析など企業の課題解決に役立ちます。ハッシュタグ検索で投稿が一覧化されるため、運営側は投稿を効率的に収集・管理できます。誰でも気軽に参加できるうえ、SNSの拡散力で投稿が自然に広がりやすいため、キャンペーン効果が出やすいのも大きな特徴です。
ハッシュタグキャンペーンのメリット
幅広い企業でハッシュタグキャンペーンがSNSマーケティングとして活用されているのは、企業にとっても参加者にとってもハードルが低く、効果的かつコストパフォーマンスの高い施策として知られているからです。
ここでは、導入コストの低さや運用のしやすさといった実施側の利点に加え、ユーザーが気軽に参加できる点など、主に「始めやすさ」にフォーカスしてその魅力を解説します。
簡単・手軽に始められる
ハッシュタグキャンペーンは、SNSアカウントさえあればすぐに始められるプロモーション施策です。従来のキャンペーンのように印刷物や会場設営などの準備が不要で、スマートフォンからの投稿のみで完結するため、企業にとっても参加者にとってもハードルが低く、気軽に取り組めます。
コストを抑えたプロモーションが可能
Web広告と比較しても、ハッシュタグキャンペーンは費用対効果に優れている点が魅力です。広告費や制作費を最小限に抑えつつ、SNSの拡散力によって自然と多くのユーザーにリーチできるため、限られた予算で高い成果を狙うことができます。
ハッシュタグキャンペーンの効果
実施することで得られるマーケティング上の成果には、認知拡大やUGCの活用、ファン化促進など多岐にわたる効果があります。
ここでは、ハッシュタグキャンペーンを通じて企業にもたらされる具体的な効果と、その背景にあるユーザー行動を解説します。
高い拡散力によりブランド認知度が向上する
SNSの拡散性を活かし、参加者が自発的に投稿することで、フォロワー外のユーザーにも情報が届きやすくなります。特にInstagramやX(旧Twitter)などは、アルゴリズム上エンゲージメントの高い投稿が露出しやすく、ハッシュタグによる二次拡散も見込めるため、自然な形でブランドの認知を広げることができます。
ユーザー生成コンテンツ(UGC)や口コミが生じる
参加者によるリアルな投稿は、UGCとして企業の資産になります。キャンペーンを通じて集まった口コミや写真、動画は、自社サイト・商品LP・広告素材などにも二次利用が可能です。また、ユーザーの投稿からインサイトを得て、今後の施策や商品開発に活かすこともできます。
顧客との接点強化とファン化が促進する
ユーザーが自らブランドを発信する体験を通じて、ブランドへの共感や愛着が深まりやすくなります。特に、投稿を企業アカウントで紹介する、コメントを返すなどの双方向コミュニケーションによって、関係性が強まり、長期的なファン化やコミュニティの形成にもつながります。
ハッシュタグキャンペーンのやり方

ハッシュタグキャンペーンを成功させるには、ただ実施するだけでなく、目的設定から効果検証までのステップを戦略的に設計することが重要です。
本章では、はじめてキャンペーンを企画する方でも実践しやすいように、準備から実施・改善までの流れをわかりやすく整理してご紹介します。
キャンペーンの目的・目標・ターゲットを明確にする
キャンペーンを実施する際は、まず「認知拡大」「UGCの獲得」「フォロワーの増加」「売上向上」など、具体的な目的を明確にしましょう。その上で、どの層に向けて行うのか、ターゲットを絞り込むことで、訴求力の高いハッシュタグや参加条件を設計できます。KPI(重要指標)の設定もここで行い、効果測定につなげます。
参考になる競合キャンペーンを調査する
目的やターゲットが定まったら、近しいテーマや業界の成功事例を調査しましょう。競合がどのようなハッシュタグを使い、どのような投稿を促していたのかを把握することで、差別化の方向性やインセンティブ設計のヒントが得られます。成功事例を模倣・分析する「マーケティングトレース」を活用すれば、キャンペーンの失敗リスクを最小限に抑えることができます。
キャンペーン内容と投稿条件を設計する
目的や競合調査に応じて、SNSプラットフォームの選択、投稿のテーマやハッシュタグ、応募方法、景品の有無・内容、実施期間などの詳細を設計します。InstagramやX(旧Twitter)など各SNSの特性を考慮し、「参加したくなる」アイデアを盛り込みましょう。ユーザーに迷わせないよう、投稿例や参加方法を明記することが成功の鍵です。
告知・拡散方法を設計する
キャンペーンの効果を最大化するには、的確なタイミングでの告知と、多様なチャネルでの拡散が不可欠です。SNS広告やインフルエンサー起用、店頭POPやレシート印字といったオフライン施策も活用すると、より広い層へのリーチが期待できます。また、キャンペーン期間中の投稿を公式アカウントでリポストするなど、双方向のやりとりも盛り上がりに繋がります。
キャンペーンツールを選定する
UGC(ユーザー生成コンテンツ)を効率よく集め、管理・分析・二次活用するには、専用のキャンペーンツールの導入が効果的です。ツールによっては自動収集・可視化・許諾管理などの機能があり、手動での運用に比べて大幅に作業工数を削減できます。
キャンペーンを告知・実施・運用する
設計が整ったら、実施フェーズに移ります。SNS上での告知だけでなく、オウンドメディアや店頭ポスター、チラシ、レシート印字などのオフライン施策も可能な限り併用して認知を最大化しましょう。公式アカウントでのリポストや、投稿に対する「いいね」など、運用時のユーザーとのコミュニケーションも盛り上がりの鍵です。
効果計測と次回施策へのフィードバック
キャンペーン終了後は、投稿数・リーチ数・エンゲージメント率・UGCの質などをKPIと照らし合わせて評価します。どの要素がうまく機能したか、どの部分が改善できるかを分析し、次回のキャンペーン設計やマーケティング施策全体に反映させることが重要です。
ハッシュタグキャンペーンの成功のポイント
ハッシュタグキャンペーンを成功に導くには、戦略的な設計とSNS特性への理解が不可欠です。ただ企画を立て投稿を促すだけではなく、ユーザーが「参加したくなる仕掛け」や「拡散したくなる導線」を丁寧に設計することで、認知・UGC・ロイヤリティの向上を同時に狙うことができます。ここでは、「投稿が集まらなかった」「思ったほど拡散されなかった」などの失敗を防ぎ、効果の最大化につなげるための実践的なポイントを解説します。
参加を後押しする心理的ハードルの低減
キャンペーン参加を促すには、「簡単にできそう」「自分にも関係がありそう」と感じてもらうことが重要です。複雑な手順や長すぎるハッシュタグは離脱を招きます。投稿ステップの簡略化や、画像付きで参加方法を説明する工夫など、誰でも直感的に参加できる導線設計がカギになります
ユーザー心理を刺激するインセンティブ設計
物理的な景品だけでなく、「投稿が取り上げられる」「共感してもらえる」といった承認欲求を満たす体験型インセンティブも有効です。例えば、「公式アカウントでの紹介」「投稿ランキングの発表」などは、参加者のモチベーションを高める要素になります。
SNSごとの拡散力を最大限に活かす戦術
SNSプラットフォームにはそれぞれ特徴があります。たとえば、Xではリアルタイム性が高く、拡散スピードが速いため短期集中型キャンペーンが向いている一方、Instagramではビジュアル表現やストーリーでの紹介が効果的です。SNSごとに投稿フォーマットや時間帯を最適化することが成果につながります。
トレンドを活用した共感・拡散の仕掛けづくり
「季節性」「話題性」「社会的関心」など、いま注目されているテーマをキャンペーンに絡めることで、ユーザーにとっての『投稿する必然性』が生まれます。例として「#夏のマイベストアイス」や「#〇〇の日チャレンジ」など、タイムリーなフックを活用しましょう。
UGCの質とブランドの整合性を高める導線設計
ただ投稿を促すだけでは、ブランドに合わないコンテンツが集まる可能性もあります。そこで、お題の提示・投稿例の掲載・撮影ルールの明記など、投稿の方向性をコントロールする工夫が重要です。ユーザーの自由度を保ちつつ、ブランドと親和性の高いUGCを集められる工夫が必要です。
投稿・拡散を後押しするコミュニケーション運用
キャンペーン中は、公式アカウントでの投稿シェアやリアクション対応を通じて参加者との関係を深めましょう。「投稿を紹介された」という体験は、ユーザーの満足度を高め、追加投稿や友人への紹介を促す好循環を生みます。SNS上の“熱量”を維持するには、こうしたコミュニケーションの積極的な設計も欠かせません。
ハッシュタグキャンペーンの重要な指標

ハッシュタグキャンペーンは実施して終わりではなく、目的達成に向けた効果検証が欠かせません。施策の振り返りを行い、次回の改善に活かすには、定量的かつ具体的な数値で評価できる「指標」の設計が重要です。ここでは、ハッシュタグキャンペーンでよく使われる主要な評価指標を3つの軸に沿って紹介します。
投稿数とエンゲージメントの把握
キャンペーンの拡散度や話題性を測るうえで、投稿数やエンゲージメントは基本的かつ重要な指標です。指定ハッシュタグを使った投稿件数や、いいね・コメント・リポストといった反応数も、ユーザーの関心度や参加意欲の高さを示すものであるのでチェックしましょう。また、表示回数に対しての反応率(エンゲージメント率)もあわせて見ることで、単なる数の多さにとどまらず「質」の部分も可視化できます。参加ハードルやインセンティブの内容によって投稿数は大きく変動するため、同業種や過去の施策との比較が重要です。
フォロワー数の変化と定着率
キャンペーンによるフォロワー増加も成果のひとつですが、施策の成否を見極めるにはその“定着率”までチェックすることが求められます。フォロワー数は「キャンペーン開始前」「実施中」「終了後」で記録をとり、増減の推移を分析します。仮にフォロワーが急増しても、終了後にすぐ離脱してしまう場合は、“キャンペーン目当ての一過性フォロー”だった可能性が高いです。こうした課題を見抜くためにも、フォロワー維持率やその後のエンゲージメント状況もあわせて追うことが重要です。
サイト流入・売上などの成果指標
ブランド認知だけでなく、商品購入や会員登録といったコンバージョン指標に繋がっているかを検証することも欠かせません。キャンペーン投稿やプロフィールリンクからどれだけ自社サイトやLPに流入があったか、また実際にどのような成果(購入・登録・問い合わせなど)を生んだかを把握します。使用する主な指標は次のとおりです。
- LPクリック数
- 購入数
- 会員登録数
- お問い合わせ件数
- SNS広告のCTRやCVR など
Googleアナリティクスや各SNSの広告マネージャーを活用することで、流入元やユーザーの行動も詳細に分析できます。
【課題×業界別】 ハッシュタグキャンペーン成功事例
ハッシュタグキャンペーンは、企業や業界ごとに異なる課題を解決するための施策として活用できます。例えば「認知が足りない」「購買につながらない」「UGCを集めたい」など、課題によって効果的なキャンペーン設計は大きく変わります。
本章では、ありがちな3つの課題を取り上げ、それぞれの課題に対してどのようなアプローチが有効だったのか、実際の事例を交えて解説します。企画の参考としてお役立てください。
認知不足を解決した事例
多くの企業が直面するのが、「自社や商品をまだ知られていない」という認知不足の課題です。このような状況において効果的なのが、SNSの拡散力を活かしたハッシュタグキャンペーンです。特に、新しいブランドや施設、サービスの立ち上げフェーズでは、スタートダッシュとして大きな役割を果たします。
キャンペーン設計の鍵は、参加者の心理的ハードルを下げることです。例えば、
- 投稿が簡単で手間がかからない
- キャンペーンの内容が面白く、参加したくなる仕掛けがある
- 当たったら嬉しいインセンティブがある
といったように、「参加するコスト<得られるメリット」と感じてもらえる企画は拡散されやすくなります。
一方、認知が十分に広がっていない段階で商品購入を参加条件にしたり、投稿の手間が大きい設計にすると、参加のハードルが上がり、想定した拡散効果が得られない可能性があります。企画を立てる際は、
- 自社は今どのフェーズにあり、誰に参加してもらいたいのか
- 参加してほしい人が自社や商品の存在をどの程度認知しているのか
- その認知度に対して、参加条件が過剰に負担になっていないか
を明確に把握したうえで、認知課題を解決できるシンプルで参加しやすい導線を設計することが重要です。
それでは、認知不足という課題に対して効果的だったハッシュタグキャンペーンの事例を取り上げ、その設計ポイントを考察していきます。
事例①:「KABUKICHO BLUE PROJECT」

【①キャンペーンの概要】
東急歌舞伎町タワー開業前の話題づくりとして、X(Twitter)で「#好きがつないでくれた」をテーマにしたハッシュタグ投稿キャンペーンです。投稿されたメッセージは、特設サイト上の“バーチャル歌舞伎町”に「言葉の雨」として降り注ぐという演出付きで表示されました。インセンティブには、同施設内のホテル宿泊券やイベント招待チケットなどが設定されていました。
【②キャンペーンの目的と背景(考察)】
このキャンペーンの目的は、開業前の施設認知と期待感の醸成と考えられます。街中で存在感はあっても「何ができる施設か」は伝わりにくく、SNSを活用した“体験型”キャンペーンによって関心を集め、情報接触を促す狙いがあったと思われます。
【③成功のポイント】
- 購買条件なしで参加できる、ハードルの低い導線
- 誰でも投稿しやすいテーマ
- 投稿数に応じた演出変化で、継続的な盛り上がり
- 自分の投稿がサイト上で演出として反映される体験
【④課題が想定される企業】
- 市場に参入し新商品・サービスのローンチを控えるスタートアップ
- オープン前から話題を集めたい商業施設・エンタメ・観光業界
- イベントや地域企画を盛り上げたい自治体・行政・地域団体
購買・集客不足を解決した事例
「商品やサービスの認知はあるのに、思うように売上が伸びない」「店舗やイベントに人が集まらない」といった“購買・集客不足”は、多くの企業にとって悩ましい課題です。情報は届いていても、実際の行動にはつながっていない──そんな状態を打開するために有効なのが、行動喚起に特化したハッシュタグキャンペーンです。
このタイプのキャンペーンは、「商品を買う」「サービスを使う」「現地に行く」といったアクションを促す設計が特徴です。特に以下のような要素が、行動の後押しとして効果的です。
- 参加者に明確なメリットがある(例:当選確率上昇や限定景品)
- 参加条件が行動に直結している(例:購入レシートなど)
- 参加することで得られる“楽しさ”や“納得感”がある
一方で、このタイプのキャンペーンは、前項で紹介した認知拡大フェーズの施策とは前提が異なります。ある程度ブランドや商品が知られており、すでに関心を持っている層が存在することを想定します。もちろん認知拡大にもつながりますが、参加条件に購入や来店といったハードルの高いアクションを含める以上、「すでに知っている人」が行動に移すきっかけとして設計するのが効果的です。
例えば、「普段からこのブランドを使っているけど、キャンペーンがあるなら別の商品を買ってみよう」「以前から気になっていたけど、魅力的な特典があるから行ってみよう」といった心理を後押しできる内容が理想です。そのためには、ターゲットを的確に絞り込み、参加までの導線を無理なく設計することが重要です。
本項でも同様に、購買・集客不足を解決した事例を取り上げ、その設計ポイントを考察していきます。
事例②:「ニベアマイレージキャンペーン2024 SUMMER」

【①キャンペーンの概要】
ニベアの新商品「肌磨きジェルクレンズ」の発売に合わせて実施された、X(旧Twitter)を活用した参加型キャンペーン。公式アカウントのフォローと、ハッシュタグ「#肌磨きチャレンジ」をつけた商品使用後の感想投稿が条件となっており、さらに商品使用中の写真を投稿することで当選確率が2倍になる仕組みが導入されていました。賞品には、高級ホテルスパ体験や、ニベアの2WAY美容洗顔アイテムなど、スキンケア意識の高い層に刺さる内容が用意されていました。
【②キャンペーンの目的と背景(考察)】
本キャンペーンの主な狙いは、新商品の購買促進と、実際の使用体験を通じた継続的な利用の後押しにあります。実際に「購入して使ってみる」ことを促す導線設計が特徴で、インセンティブや投稿条件を工夫することで、参加への動機づけが強化されています。特に、画像投稿による当選確率アップや、オリジナル画像が作成できるジェネレーターの導入など、ユーザーが積極的にUGC(使用感や写真)を投稿したくなる仕掛けが設けられており、結果として購買を促しながらSNS上での拡散・話題化も実現しています。
【③成功のポイント】
- 使用体験とセットになった投稿条件により、購買行動を自然に促進
- 画像付き投稿の促進とインセンティブ設計による参加率の底上げ
- 投稿者のモチベーションを上げる「画像ジェネレーター」
- 「スキンケアに励む自分を肯定できる体験」を演出し、SNS投稿の心理的価値を高めた点
【④課題が想定される企業】
- 使用体験が購買促進に直接つながるスキンケア・コスメ・電化メーカー
- 新商品販売のタイミングなどで集客・話題化を狙いたい食品・飲食
口コミ・UGC収集不足を解決した事例
企業が抱える課題の一つに、「口コミやUGC(ユーザー生成コンテンツ)が十分に集まらず、利用者のリアルな声を商品開発やサービス改善に活かせない」ということがあります。従来のアンケートやレビューだけでは、実際の生活の中でどのように商品が使われているのか、何に困っているのかといった“ユーザーの視点”を拾いきれないケースが多くあります。その結果、商品やサービスの改善に必要な情報が不足し、ユーザーが求める価値に寄り添った開発・コミュニケーションが難しくなるという課題が生まれます。
この課題が表面化するのは、すでにある程度の認知度や購買行動が獲得できており、ブランドとの接点を持つユーザーが一定数存在するフェーズです。この段階では、さらに多くの人に知ってもらうこと以上に、「実際に使っている人がどう感じているのか」「どんな改善が求められているのか」といったリアルな声の収集が、今後の成長戦略で不可欠になります。
UGCを集めるハッシュタグキャンペーンは、こうしたフェーズにある企業において特に有効です。ただし、認知や購買を目的としたキャンペーンと同様に参加のハードルが高くなるため、以下のような設計ポイントが重要です。
- ターゲットを既存ユーザーや利用経験者にある程度絞る
- ユーザーが思わず投稿したくなる日常の課題や共感されやすい体験を題材にする。
- 投稿すると解決策がもらえる、公式から反応がある、特典が当たるなど心理的・実利的な価値を用意する。
- UGCが商品開発やサービス改善に活かされることを明示する。
このように、UGC不足を解決するキャンペーンは、単に投稿を集めるだけでなく、ターゲットを明確に設定し、参加するハードルと得られるメリットのバランスを最適化することで、利用者のリアルな声を効果的に収集できます。これにより、ブランドとユーザーの関係を深めつつ、次の成長フェーズに必要なインサイトを獲得できます。
本項も同様に、口コミ・UGC収集不足を解決した事例を取り上げ、その設計ポイントを考察していきます。
事例③:「#検索できない家事ストレス をボヤこうキャンペーン」

【①キャンペーンの概要】
カビキラー、dinos、デコホームの3社による共同キャンペーンです。X(旧Twitter)で「#検索できない家事ストレス」のハッシュタグをつけて、家事に関する“ちょっとした悩み”を投稿すると、各社のお助け隊がリプライで解決方法を返してくれるという内容です。さらに、投稿者の中から抽選で100名に“お助けグッズ”がプレゼントされるインセンティブも用意されていました。
【②キャンペーンの目的と背景(考察)】
本キャンペーンの主な狙いは、「生活者のリアルな悩みを可視化すること、共感と会話を通じてブランドとの接点を作ること」にあります。UGCによって集まった投稿は、単なるデータではなく、次なる商品開発やコンテンツ設計に活かせる“生活のインサイト”として機能します。
また、各投稿に対して企業アカウントがリプライするという設計は、単なるUGC収集にとどまらず、双方向のコミュニケーションを重視する点で非常に優れたキャンペーンです。リプライのやりとりが発生することで、Xのアルゴリズム上も“おすすめタイムライン”に載りやすくなり、投稿の拡散効果が高まる工夫がされています。
【③成功のポイント】
- 共感しやすい「家事の小さな悩み」をテーマに設定
- 投稿に対する公式アカウントからの丁寧な返信で、参加者満足度が向上
- 投稿・返信のやりとりがアルゴリズム上の拡散を後押し
- UGCを「投稿で終わらせない」設計で、ブランドの課題解決力を印象づけ
【④向いている企業】
- 生活に密着したプロダクトを扱う日用品・生活雑貨メーカー
- 顧客の“悩み”や“使い方”をコンテンツに活かしたいSaaS・ITサービス
- SNSを通じてユーザーとの関係構築を重視する美容・食品業界
- ターゲットの生活実態を把握し、次の施策につなげたいブランド全般
ハッシュタグキャンペーンの問題点
ハッシュタグキャンペーンは、認知拡大から購買促進まで幅広い効果が期待できる一方で、設計や運用に問題を抱えることもあります。ここでは、実施時に陥りやすい代表的な問題点と、それを回避するための視点を紹介します。
UGCの「質」の担保が難しい
キャンペーンを通じて多くの投稿が集まったとしても、企業のブランドイメージや目的に沿った投稿が少なければ、思うような効果は得られません。特にUGCを二次活用(広告やサイト掲載)する場合、「投稿数」より「投稿の質」が重要になります。「#◯◯のある暮らし」といったハッシュタグを例に挙げると、どのような写真やシーンを集めたいのか、事前に参考例を提示するなどして設計しておくことが重要です。
SNSごとのユーザー傾向を無視した設計
X(旧Twitter)では拡散力、Instagramではビジュアルの訴求力、TikTokでは音楽やエンタメ性が重視される傾向にあります。これらの特性を理解しないまま、一律の内容でキャンペーンを展開すると、ターゲットユーザーの関心を引きにくくなります。SNSごとの「使われ方」に合わせた演出やハッシュタグの設計を怠ると、せっかくの投稿も埋もれてしまい、費用対効果が下がってしまいます。
ステルスマーケティングと誤認されるリスク
投稿内容を過度に誘導してしまうと、「自然な投稿」ではなく「企業の宣伝」とみなされ、ステマ(ステルスマーケティング)と誤解されるリスクがあります。結果として企業イメージの低下や炎上につながる可能性も0ではありません。そのため、参加者に「自分の言葉で語ってもらう」工夫が必要です。例として、特定のキーワード使用を必須とせず「#〇〇体験」「#〇〇との思い出」といった、個人の体験を引き出す柔らかな設計が効果的です。
運用工数が想定より掛かる
手軽に始められる印象のあるハッシュタグキャンペーンですが、実際は投稿管理、抽選、当選者対応、二次利用許諾の取得など、裏側では多くの運用工数がかかります。反響が大きいほど問い合わせや対応も増えるため、事前にフローを整備し、場合によってはツールの導入を検討することも必要です。
ハッシュタグキャンペーンの注意事項

ハッシュタグキャンペーンは手軽に見えて、実は配慮すべき点が多くあります。SNSプラットフォームごとのルール違反によるアカウント停止リスクや、法令(景表法・著作権・個人情報保護法など)の遵守、さらにはユーザーとの信頼関係を損なう炎上リスクまで、実施時には注意点を事前に把握しておくことが欠かせません。以下では、トラブルを未然に防ぎながら、安心してキャンペーンを実施するための重要なポイントをご紹介します。
SNSプラットフォームのガイドラインを遵守する
各SNSには独自のガイドラインや禁止事項があり、これに違反すると投稿の非表示化やアカウント停止など重大なペナルティにつながります。たとえば、Instagramでは「フォローやいいねを条件にプレゼント提供」する手法がガイドラインに違反する場合があります。また、Twitterでは「複数アカウントを用いた応募」が不正行為とされ、キャンペーン全体の信頼性を損なうおそれもあります。実施前には、各SNSの「キャンペーンポリシー」「コミュニティガイドライン」「スパム規約」などを確認し、ルールを守った設計を心がけましょう。
法令遵守とステマ・著作権の配慮
ハッシュタグキャンペーンでは、以下のような法律や規制にも注意が必要です。
- 景品表示法:景品の金額や当選者数に上限があり、違反すると措置命令や課徴金の対象になります。
- 著作権・肖像権:UGC(ユーザー生成コンテンツ)の二次利用時は、必ず投稿者から使用許諾を得る必要があります。
- 個人情報保護法:応募者の氏名や住所などを収集する場合、利用目的の明示と同意取得が必須です。
- ステマ規制:PRであることを明記せずに投稿を促すと、ステルスマーケティングと見なされるリスクがあります。
ガイドラインやキャンペーン規約で「同意の取得方法」「使用範囲」「責任範囲」などを明示しておくと安心です。
炎上・トラブルを回避するための工夫
一見盛り上がっているように見えるキャンペーンでも、設計次第では炎上のリスクがあります。たとえば以下のようなケースです:
- 当選者の選考基準が不明瞭で不信感を招く
- 抽選の公平性に疑問が持たれる(例:同じ人ばかり当選)
- ハッシュタグが誤解を招く表現になっている
- 特典の発送遅延や問い合わせ対応が不十分
こうした事態を避けるには、キャンペーン参加条件の明確化、想定質問へのFAQ整備、迅速なカスタマー対応体制の構築が必要です。
UGCの二次利用には必ず許諾を取る
SNSキャンペーンの投稿を広告やLPに二次利用する場合は、必ず投稿者の許諾を取得しましょう。「投稿をもって利用許諾に同意したものとみなす」旨をキャンペーン規約に明記したり、応募時のフォームで同意チェックを設けたりするとスムーズです。また、使用範囲(Web/SNS/広告など)や期間、加工の有無についても事前に明確に伝えておくことが、トラブル防止につながります。
ハッシュタグキャンペーンまとめ
ハッシュタグキャンペーンは、SNSの拡散力を活かして商品・サービスの認知拡大やUGC(ユーザー生成コンテンツ)の創出を促す、非常に効果的なプロモーション手法です。
一方で、成功には「企画の質」と「運用の丁寧さ」が欠かせません。SNSごとのルールやユーザー特性を踏まえたうえで、明確な目的設計・ターゲット設定・KPI設計を行いましょう。
本記事で紹介したように、成果を高めるためには、ただ投稿数を追うのではなく、エンゲージメントやコンバージョンなどの指標まで丁寧に分析する姿勢が重要です。
また、法令やプラットフォームのガイドラインを遵守することで、炎上やアカウント凍結といったリスクも防げます。
これからハッシュタグキャンペーンを始めたい方も、過去に実施したものを改善したい方も、ぜひ本記事の内容を参考に、成果につながる企画を実践してみてください。
口コミ創出ならAha!のUGCパッケージ!
Aha!のUGCパッケージは、ユーザーが自発的に商品やサービスの口コミを投稿する仕組みを構築し、その声をSNSで大きく拡散します。
アレンジレシピや利用シーン投稿、大喜利形式など、多彩な企画スタイルに柔軟対応。ハッシュタグや専用サイトで投稿をまとめ、コンテンツとして活用できるため、キャンペーンの効果を持続的に高められます。
さらに、当選連絡や賞品発送といった事務局業務も丸ごとサポート。「どんなテーマで募集すれば盛り上がる?」といった企画面のご相談にもプロが丁寧に対応しますので、まずは無料相談・お見積もりからお気軽にご相談ください。